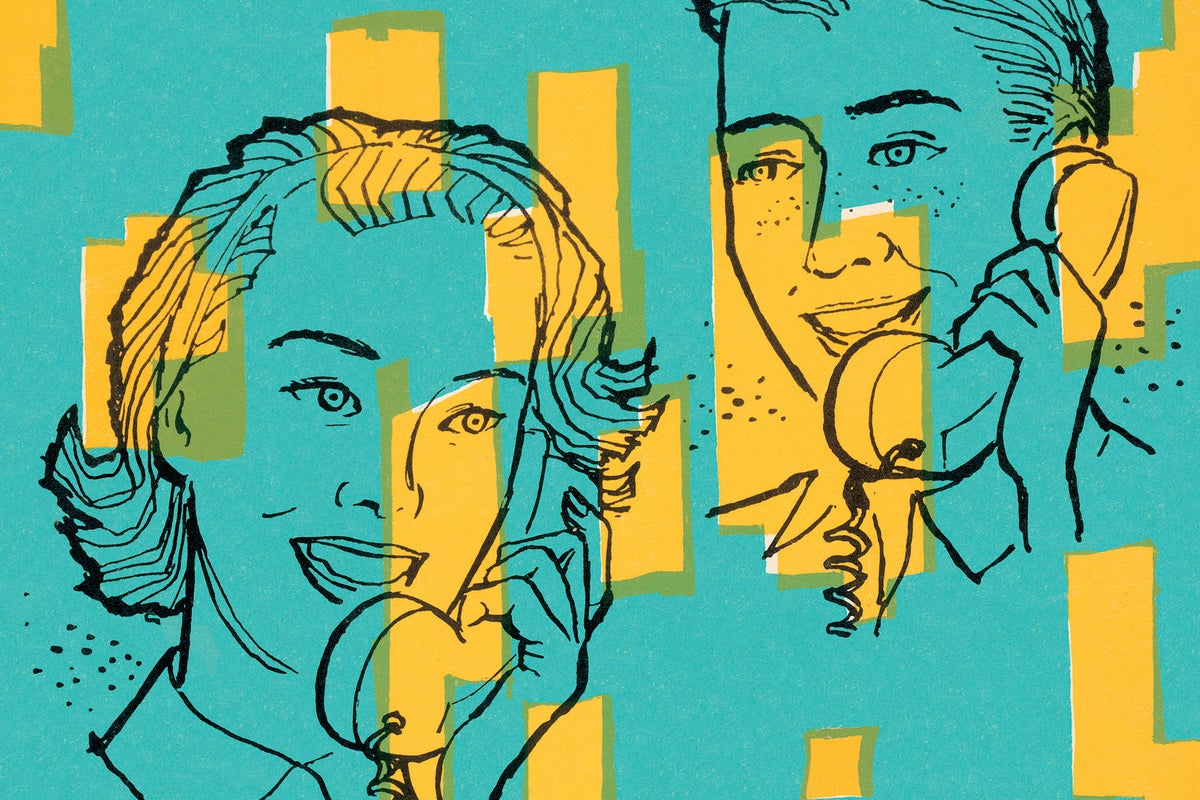- The Rest Is Sheep
- Posts
- #060_Sheep キャッチアップ・カルチャー
#060_Sheep キャッチアップ・カルチャー
友人と会うたびに「最近どう?」と近況報告を交わし、数時間後には解散。次に会うのはまた数ヶ月後──。現代の大人の友人関係は、一緒に何かを体験するのではなく、お互いの生活を要約して報告し合う「キャッチアップ・カルチャー」に偏っている。SNSで繋がっているようで実は孤独を感じ、効率性を追求するあまり友情の深さを失っていく。学生時代のような自然な交流はもう取り戻せないのか。この構造的な問題にどう向き合えばいいのか。現代社会における友情のあり方を問い直す。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。
役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。
そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。
↓無料登録はコチラから↓
🔍 Sheepcore
カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。
キャッチアップ・カルチャー

©️The Rest Is Sheep
🐏「すみません、遅くなっちゃって」
🐕「いえいえ、お疲れさまです。仕事関係の会食だったんですか?」
🐏「いや、地元の友人で、今でも年に一回とか二回とか、会って軽く飲んだりしてるんですけど」
🐕「良いですね、長く続く友人」
キャッチアップ・カルチャー
🐏「数少ない友人の一人です(笑)でもなんか、最近の友達との交流ってほとんど飲みながら近況報告じゃないですか?」
🐕「あー、いわゆる「キャッチアップ・カルチャー(catch-up culture)」ですね」
🐏「キャッチアップ・カルチャー?」
🐕「簡単に言うと、現代の大人の友人関係が「何か一緒にする」から、「お互いの生活の要約を報告し合う場」になっちゃってるっていう現象です」
🐏「あー、まさにそれです(笑)。前回会った時からの「差分」を埋める作業っていうか」
🐕「昔はもっと、生活の延長で友達と一緒にいましたよね」
🐏「授業後にダラダラ喋って、スーパー行って家で飲んで、週末は旅行…そういう「生活の共有」が友情だった」
🐕「いまは予定合わせて店予約して、数時間で「アップデート交換」して解散」
🐏「社会人になると住む場所も働き方もバラバラになるし、パートナーや家族ができると、学生時代みたいな「物理的な近さ」と前提としたコミュニティは維持しづらいですしね」
🐕「もちろんキャッチアップ自体は楽しいんですけど…」
🐏「年々忙しくなって、話すだけで時間が終わる」
🐕「交流が「メンテナンスチェック」になってるんですよね。友達関係を維持するための「点検」みたいな感じになっちゃって、関係を深めるための「投資」じゃなくなってるんですよね」
SNSがもたらした「つながっているという錯覚」
🐏「しかも、SNSがこのキャッチアップ・カルチャーをさらに複雑にしてる気がするんですよね。SNSで繋がってるから、実際には会ってないのにどこか「相手の生活を知っているような気になる」みたいな感覚がある」
🐕「ほんとそうですよね。SNSは本来、距離を埋めるツールだったはずなのに、今は「知っているつもり」の錯覚を生み出してる」
🐏「SNSに投稿してる情報なんて、本人たちが「見せたいようにキュレーションした」ハイライトだけなのに(笑)」
🐕「「最近ポストしてたあれ、どうだった?」みたいな、中途半端な知識を前提にした会話が始まっちゃう。便利なようで、親密さを育むための小さな出来事や感情の機微を拾い上げるステップを飛ばしちゃってる感じがしますよね」
🐏「しかも、インスタ見て「あ、あいつヨーロッパ旅行に行ってたんだって思って、リアルでキャッチアップする時に「旅行どうだった?インスタ見たよ」って聞いたが最後。旅行中にあげたストーリー全部見てる前提で話進んじゃったりもして(笑)」
🐕「そこまで見てねえよと(笑)」
🐏「相手によっては逆に「SNS全部見てるって思われるのもな、、、」って思って、旅行行っこととか知らない振りして気を遣ったり(笑)」
🐕「めんどくさいですね(笑)」
🐏「はい(笑)」
🐕「「情報過多による親密性の希薄化」っていうパラドックスですよね。かつてないほど他者の情報にアクセスできるようになった。でもその多くは「キュレーションされた情報」で、本当の感情や日々の葛藤といった「生の情報」じゃない」
🐏「デジタル時代が生んだ、友情の皮肉ですね」
🐕「ちなみに、研究でも「SNSの利用時間は増えてるのに、孤独や断絶感はむしろ上がってる」って話が結構出てるんですよね」
🐏「SNSのつながりが逆効果ってことですね」
🐕「はい、「友だちの数」は増えても、「支えられてる実感」は増えない、みたいな」
🐏「フォロワーが1,000人いようが、夜中に「話聞いて」って言える相手は1人もいない」
🐕「はい、さらに、SNSのつながりを広げすぎるほど1人ひとりとの「近さ」は薄まるっていう研究もあって」
🐏「うーん、分かる気がします」
🐕「だから今の友情って、「画面の向こうではつながってるのに、現実世界では孤独」っていうパラドックスを抱えてるんですよね」
🐏「SNSで世界とつながるほど、リアルの人間関係が薄まっていく…これもまた皮肉ですね」

BBC
友人関係は劣後する
🐕「もうひとつ、異性愛規範(ヘテロノーマティヴィティ)的な価値観も関係してるって言われてますよね」
🐏「というと?」
🐕「ぼくらって、「大人になったら異性のパートナーと一緒に暮らす」っていうライフスタイルを刷り込まれてるところがありますよね。だから友情はその「外側」にある関係として扱われがち」
🐏「あー、なるほど、、、」
🐕「仕事や自身のスキルアップ、恋愛関係、そしてインスタ映えする瞬間を優先するように社会的に奨励されている。そういう活動が「生産的」だって見なされて、友人とただだらだら過ごす「非生産的な時間」が切り捨てられちゃう」
🐏「言い方悪いですけど、カップルでの同居は、シェアハウスみたいな友達との共同生活より「人生一歩進んでる」みたいな雰囲気ありますもんね(笑)」
🐕「パートナーがいない人も、「友人と過ごす時間」より「パートナー探し」の方を優先しがち」
🐏「それ自体は悪いことじゃないんですけど、どうしても友人との時間の優先度は劣後しますね」
🐕「感情面でも、悩みや孤独を友人に打ち明けたりってあまりしないですよね」
🐏「友人に「寂しい」とか「もっと日常を共有したい」と言うのはちょっとおこがましいっていうか、依存しすぎって思われるんじゃないかって感じます」
🐕「結果、感情的に深いつながりとか「偶発的な」要素ががどんどん減って、スケジュール管理された機能的な友人関係になってしまう」
🐏「効率はいいけど、みんな仕事や家庭、自己管理で手一杯。友達との時間は「会議」みたいに事前調整して確保するしかない」
🐕「友情や関係が「取引的な瞬間(transactional instances)」として感じられてしまうこと、確かにありますね」
「キャッチアップ・カルチャー」とどう向き合うか
🐏「うーん...じゃあ、どうすればいいんですかね」
🐕「難しい質問ですね(笑)。簡単な答えはないと思うんですけど」
🐏「ですよね。もう、多忙な現代人が、大学時代のような自発的な交流を取り戻すのは不可能なんじゃないかとも思うんですけど」
🐕「たとえばニューヨークに住む31歳の女性、Amani Orrは自身の社交生活を「ディナーと飲みの絶え間ないサイクル」って表現してるんですけど」
🐏「ああ、わかりみが(笑)。友人関係が、いつも「食事に行く」「近況を報告し合う」「解散」っていう同じパターンに固定されちゃってる(笑)」
🐕「現代の友情が「食事や飲み会の繰り返し」に矮小化されてる。なので彼女は単なる夕食や飲み会をやめて、一緒に用事をこなす、新しいスポーツをする、一緒に料理をする、美術館に行くみたいな「お互いにとって負担になりすぎないようなアクティビティ」をスケジュールするようにしたそうです」
🐏「「報告」じゃなくて「体験」を共有するってことですね」
🐕「はい、スーパーでの買い出し中や、スポーツ後の帰り道での何気ない会話みたいな、親密さを育む「生の情報」を作り出すアクティビティ・ドリブンな交流」
🐏「友人と久々に連絡とっても、つい「今度飯でも行こっか」って言っちゃいますよね。それやめてみるっていうのはありかもですね」
🐕「ですね」
🐕「ロンドン在住のコンテンツクリエイター、Nicole Soも、友達と会ったときに「最近興奮したこと」「落ち込んだこと」「興味深い経験や学び」を聞くようにしたって」
🐏「「何があった?」じゃなくて「どう感じた?」に焦点が移る感じ?」
🐕「まさに。彼女がTikTokでキャッチアップ文化について投稿したら、たくさんの友達が「自分も同じこと感じてた」って連絡してきて、今は実践してるらしいです」
@nicoleso__ my lil evening spiel, what do you guys think? #friendships #catchups #growingup #adultfriendships #reflection
🐏「われわれもこうやって飲み行ってばっかなんで、関係性見直してみましょうか(笑)」
🐕「ははは、そうですね(笑)」
🐏「来年こそスパルタンレースエントリーしましょうよ(笑)」
🐕「…前向きに(笑)」
🎙️ポッドキャストはコチラ!
※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕
🐏 Behind the Flock
“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。
1. キャッチアップだけの友情関係
大人になると、友人との関係は「近況報告」中心に変化し、かつてのような自然で深い会話が難しくなる。会えば「仕事は?家族は?」と情報交換に終始し、本音や悩みといった大事な部分が置き去りになる。背景には、家庭や仕事の優先順位、生活環境の変化、そして情報過多による心の余白の不足がある。専門家も、共有体験が減るほど会話は表層化しやすく、互いに余力がないため深い交流を避けてしまうと指摘する。ただし、短いキャッチアップ自体は孤立を防ぐ役割もあるため、問題は量ではなく「比率」だという。普段の近況報告に加え、ときには悩みを共有したり、会う前に「今日は深く話したい」と意図を伝えたり、過去の会話をフォローするなど、小さな工夫が関係を再び豊かにする鍵になる。
2. キャッチアップの罠
現代の友情は、忙しさから「キャッチアップ・トラップ」に陥りがちだ。久々の再会が近況報告と愚痴の応酬になり、かつてのような「一緒に生きている」感覚が薄れてしまう。Life Uncut Podcastの出演者たちは、友人との時間が「近況の報告」に終始し、笑いや共有体験が失われている現状を指摘。この気づきはSNSでも多くの共感を呼び、友人と「もっと一緒に何かをしたい」「思い出を作りたい」という声が相次いだ。解決策はシンプルで、ただ会って話すのではなく、映画やボウリング、陶芸など「新しい体験」をともにすること。日々の報告はテキストや音声で補い、対面の時間は感情が動く体験に使うのが理想だ。手間はかかるが、深い友情は人生の充実や健康にもつながり、長く続く関係を育てる鍵になる。
3. キャッチアップをやめて、ハングアウトを始めよう
現代では友人関係が「キャッチアップ中心」になり、気軽に「ただ一緒にいる」時間(= ハングアウト)が失われつつある。キャッチアップは予定を入れて近況報告を交換する行為で、効率的だが形式的。一方ハングアウトはソファでだらだら過ごすような非構造的な時間で、大人数にも広がりやすく、予期せぬ展開が生まれる。しかし社会生活はコロナ以降ますます予定化、商品化され、短時間の予定が細切れに積み重なる「Time Confetti」が進行。都市の高コストや住環境の狭さ、移動時間の長さも自発的な集いを阻む。その結果、人びとは多くの友人と浅くつながる一方、深い関係を築きにくくなる。予定に縛られた「義務的な会合」ではなく、偶発性のあるハングアウトこそ本来の人間的な社交なのだ。
🫶 A Lamb Supreme
The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。
今週もお休みです 🐏
すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑
この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。
このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。
↓定期購読はコチラから↓