- The Rest Is Sheep
- Posts
- #005_Sheep 新春特別講義2:アルゴリズムは文化をつまらなくしたか(後編)
#005_Sheep 新春特別講義2:アルゴリズムは文化をつまらなくしたか(後編)
文化の停滞をアルゴリズムのせいにする議論は表層的だ。アーティストの活動を困難にする経済格差や社会構造こそが、より本質的な問題として議論されるべきである。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。
役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。
そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。
🔍 Sheepcore
カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。
新春特別講義2:アルゴリズムは文化をつまらなくしたか(後編)
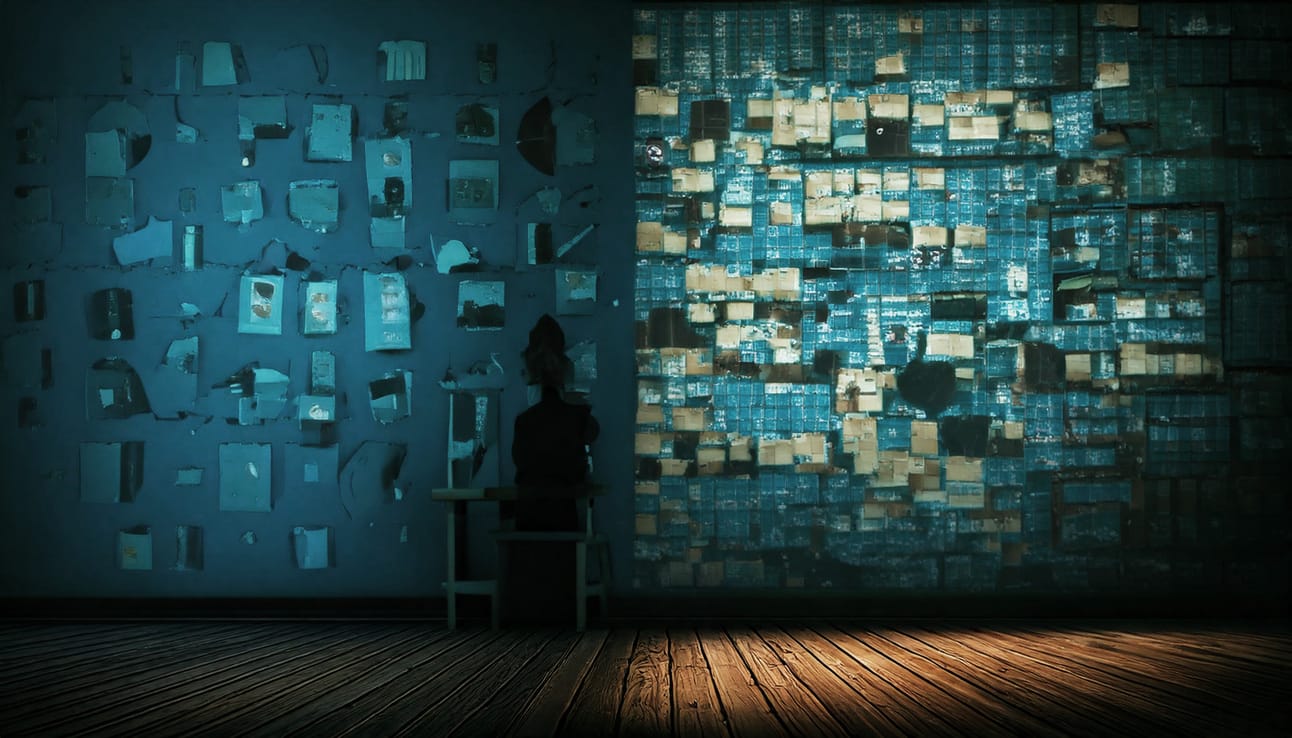
©️The Rest Is Sheep
(前編から続く)前編はこちら🔍
さてさてその上で、今日は「文化や芸術について語るんなら実は他にも重要な問題があるんじゃないの?」という話です。私たちの文化を何かが揺るがしているとして、文化的アルゴリズムにすべての責任を負わせるのは違うんじゃないの?と。
例えば、都会のライブハウスやアトリエの家賃が高すぎて若いアーティストが活動できない。音楽や芸術で生計を立てることが難しくて、創作活動に専念できない。音楽ライブの会場が高級マンションやオフィスに取って代わられている。Spotiryのレコメンデーションが音楽の幅を狭めてるとか、アルゴリズムを批判するのは容易いけれど、こういった現実も文化の衰退に大きな影響を与えているんじゃないでしょうか。
アーティストの中にも「自分の作品がインフルエンサーに取り上げられない」「自分の楽曲がトレンドのキーワードにうまく引っかからない」「アルゴリズムに嫌われてる」と嘆く人がいます。売れるコンテンツを制作する、という観点で「アルゴリズムとの相性」は重要かもしれません。
でも、その言葉の奥深くには「もう自分の居場所がないのではないか」という、アーティストとしての深刻な不安があるんです。消費者に響かない、売れない、もう自分の居場所はない、生き残れないんじゃないか。じゃあその不安って、文化的アルゴリズムが取っ払われば解決される話なんでしょうか?本当にそう思って文化的アルゴリズム批判をしてます?それより、アーティストがアーティストとして活動できない、才能あるアーティストが創作活動に専念できない、そんな社会構造にこそ問題があるんじゃないでしょうか。
InstagramやSpotifyのレコメンデーションのアルゴリズムは確かに画一的な感じがするし、それによってコンテンツとの出会いがコントロールされていると言われれば、そりゃそうですよね(笑)。それも重要な問題です。でも、私たちの文化や芸術にとってよりより本質的かつ深刻な問題は、InstagramやSpotifyのレコメンデーションのアルゴリズムだけにあるのではなくて、その上流にあって、私たちの生活に深く関わる領域にも存在するんです。でも、アーティストたちも、私たちも、上流の領域にある大きく強力な構造に意義を申し立て、そいつらを変えてやろうとするにはあまりに無力で、そんなもの変えられっこないとハナから思い込んでる。
だからこそ、アーティストの作品が私たちに届く、あるいは届かずに玉砕する(笑)頃には、批判の矛先は一番分かりやすい最下流の配信メカニズム、例えばSpotifyやInstagramへと向けられて、批評家たちのもっともらしい整理とともに、文化的アルゴリズムを巡る論議が沸き起こる。「我々は真に作品を楽しんでいるのか、それともアルゴリズムの操り人形に過ぎないのか」と。これで一丁上がりです。
えー私、冒頭みなさんに質問しました。「YouTubeやTikTok、Instagramをなんの気なしに見始めたと思ったら次から次へとレコメンデーションされるコンテンツを見続けちゃった、みたいな経験ありますか?」と。文化的アルゴリズムの問題は私たちの手のひらの距離で、日々使っているアプリの話で、日常の体感値があるので、そうした体感に寄り添う形で、かつちょっと新しい切り口で整理をされると「あーそうそう、確かにねえ」という腹落ち感を感じやすいんですよね。
批評家たちは、オンラインでの行動がアルゴリズムによって追跡され、パーソナライズされたコンテンツが提供されることに関してアーティストや私たち消費者が抱える漠然とした不安感に「アルゴリズム不安」―英語でいうと 'algorithmic anxiety' ですが―まあこういったラベリングをして、その原因はスマートフォンやアプリ、そしてその裏側にあるアルゴリズムにあるんだ、と示唆しています。これは、文化的アルゴリズムを文化の停滞の戦犯として断罪するという、これまで見てきた主張とともに、現在の文化をめぐる状況を鋭く表しているかのように聞こえます。これもなんか、納得感ありません?「アルゴリズム、まあ、確かに気持ち悪いよなあ」と。
繰り返しになりますが、たしかにそこには問題が無いわけではないんです。隙間時間にちょっとアプリを開いて目に飛んできたショート動画の続きが気になってついつい最後まで、といっても数十秒ですよ?つい終わりまで見ちゃったようなコンテンツとそっくりな動画が延々と推薦されてくる。で、流れてくれば見ちゃうのが人情なんですけど(笑)、それ、本当に自分にとって必要なコンテンツか?って言われたら、いやまあ見たのは自分だけど、確かに時間の浪費以外のなにものでもない(笑)。
アプリの胴元からすると、私たちが画面に目を向けている時間が増えれば増えるほど広告収益の機会が増えるわけで、結局そういう無駄なコンテンツがアルゴリズムの名のもとにレコメンデーションされ続ける。まあ、どうかと思います(笑)。マジで誰かなんとかしてほしい(笑)。
まあ、こういうイチャモンは酒の場の会話のネタにもなるし、さっき話した通りみんな何かしら体感がある話なのでついつい盛り上がっちゃうわけです。でも、文化的アルゴリズムへの過度の注目は、私たちが考えなきゃいけないもっと大きな問題を覆い隠しちゃってる。社会の不平等や格差、その中で文化や芸術がどう扱われているか、扱われるべきか。今日は時間の関係で細かくは触れませんが、そうした領域においてもテクノロジーは使用され、アルゴリズムは広く活用されています。そして、その領域におけるアルゴリズムの使用にこそ、問われるべき問題が存在します。
あー、そろそろ時間ですね。みんな腹減ってますよね?ソワソワしてきた(笑)。ええと、私たちは、文化的アルゴリズムにばかり注目するのではなく、もっと大きな視点を持つ必要があるんだ、最後に改めてこの一言だけ皆さんにお伝えして、今日の講義を終えたいと思います。この視点は、今後の授業の中でさらに皆さんと議論を深めていきたいと思います。えー、私がSpotifyさんの、えー、圧力、というと物騒ですかねえ(笑)、まあ、何らかの干渉(笑)、により途中でクビにならなければ、ですけどね(笑)。では今日はここまで。お疲れさまでした。
🐏 Behind the Flock
“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。
1. 「アルゴリズム不安」の時代
ある日突然同じ商品の広告が複数のプラットフォームで同時に表示されるようになったり、独身になったとたんInstagramがモデルのアカウントをレコメンデーションし始めたりする。「アルゴリズム」という曖昧で、影のある、非人間的な存在が、無意識のうちに自分の行動を操作しているように感じさせることに由来する「アルゴリズム不安」と呼ばれる不安感を、多くの人びとが感じている。
2. 高騰する家賃と進む不動産開発、イギリスの芸術は生き残れるか?
ロンドンでは、家賃の急騰や不動産開発により、2020年以降スタジオの数が半減し、ギャラリーやアーティスト運営のスペースの閉鎖が相次いでいる。この影響で、多くのアーティストが創作の場を失い、活動を諦めざるを得ない状況に追い込まれている。イギリスのアートシーンを守るためには、政府や自治体、デベロッパーがアーティストコミュニティと協力し、創作活動を安心して続けられる環境を構築することが急務となっている。
3. 住宅ローン審査アルゴリズムの裏に隠されたバイアス
今やInstagramやSpotifyなどだけではなく、その上流で私たちの生活に深く関わる領域(金融、医療、司法など)にこそアルゴリズムが広く活用されている。そして、これらの領域で使用されるアルゴリズムが、開発者によるバイアスの影響を受け、構造的な不平等や差別を助長するケースも少なくない。The Markupによる2021年の調査では、米国の黒人の住宅ローン申請者は、同じような経済的背景を持つ白人の申請者と比べて、アルゴリズムによる査定エンジンによって融資を拒否される可能性が80%も高いことがわかった。
🫶 A Lamb Supreme
The Rest Is Sheepが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。
Behind the Flockでも言及した「アルゴリズム不安(Algorithm Anxiety)」に対するカウンターカルチャーとして、人間が主体的に情報やコンテンツを選択・共有するコミュニティが世界的に広がりをみせていますが、その一例として、2023年にニューヨークで始まった『Reading Rhythms』をご紹介。
忙しい都市で読書の時間を見つけたいという思いから、ニューヨークの屋上に集まった友人たちによって始まったこのコミュニティは、音楽と読書を組み合わせた独自のアプローチと、オフラインとオンラインを組み合わせたハイブリッドな運営が特徴的です。アルゴリズムによる推薦ではなく、参加者同士の対話と共有を重視したこの取り組みは、現在では世界的なコミュニティへと成長を続けているそうです。デジタル時代における新しい読書コミュニティ。
すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑
この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。
このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。
↓定期購読はコチラから↓





